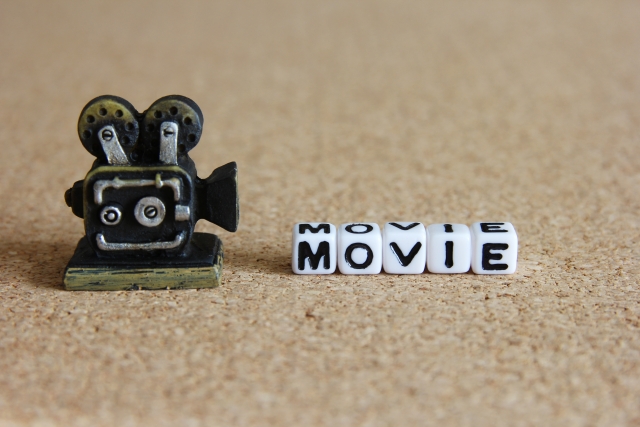この記事では、
映画「万引き家族」についての感想を掲載しています。
<ネタバレ>も含まれますので、ご注意下さい。
はじめに
今日は東京で雪が降る。冷え込むことは必至だった。
ベランダで吸うタバコの火さえも、なんだか暖かく感じられる。
だからこそ、今日は身体を温めるためにコーヒーを飲みながら、映画をみる。
寒さが身に凍みる日は、淹れたてのコーヒーといい映画。そう相場は決まっているのだ。
さて、是枝監督の最新作「万引き家族」を同情という感情で汚すことは許されない。
貧しさや万引きという行為を「弱さ」と決めつけ、さらにそこに哀れみをかけることは、この作品の意図するところではないだろう。
同情とは人間がもつ感情のうちでもっとも愚鈍な感情の一つである。
なぜなら、同情にはいつも「羞恥心」が欠けているからだ(ニーチェ『ツァラトゥストラかく語りき』)。
同情する人は、悩んでいる者、貧しき者の中に土足で踏み入り、彼/彼女の生を矮小なものにする。
「君の生はあまりにも卑小で可哀想なものだ。私と比較して」
だから同情する人は、厚顔無恥にも、彼/彼女らに「弱さ」を刻印し、来世での幸せを説く。
「今の君の生は、どうしようもないほど可哀そうものだ。だから来世に期待しなさい」と。
同情とはなんと恥辱が足りないことか。
そいつは彼/彼女の一体何を知っているのか?
すべてを憶測によって判断され、勝手に哀れまれてしまうことの、傍若無人さをわれわれは考えなければならない。
このことは、この映画を見たものならば、誰でも納得できることだろう。
なぜなら、この「家族」はひどく高貴なのだから。
以下はネタバレを多く含むがゆえに注意が必要である。
また以下は私が解釈する一本の線であり、この解釈の正統性を主張することは私の意図するところではない。
以下は、私の身体に起きた「触発」を忘れぬよう書き記しておくための備忘録である。
いまだ知られざる星座としての新たな集団性
不可知の関係性
人と人との関係とは何によって規定されるのだろうか。
血縁、地縁?
この解答は、われわれの目を曇らせる。
その解答は、思考停止と同じである。
それは、あらかじめ決められた関係性によってしか、その関係を評価させなくしてしまうからである。
しかし、点でバラバラで、単にそれが集まった雑多な集団というわけでもない。
彼らはある形をもった、一つの「集団性」を形成しているからだ。
この映画では生活に必要なものが「万引き」によって調達される。
だからこそ、祥太もりんも、ある意味で万引きされる(拾われる)ことで家族になっている。
誰も血のつながりもなければ、最初に名付けられた名前も使っていない。
あらゆる意味で「偽 - 家族」的なのだ。
したがって、この映画で描かれている関係性は、われわれのもつ常識的で単純な尺度では、推し量ることはできないのだ。
「家族」は形成される
ところで家族とは本来はこのようなものなのではないだろうか?
常にわれわれはどこからかやってきては誰かのもとへと流れ着く。
それは今現在、母親と呼び慕っている人物のもとであったり、今横にいる最愛のパートナーのもとであったり。
自分に子供ができる時、拾うことと、産むことに差異はあるのだろうか。
無論、女性にとっては大きくあるだろう。
なぜなら、彼女らはお腹を痛めて子を産むからである。
しかし、それ以外は?
特に男にとっては?
まったくと言っていいほどに、そこに差異を見出すことができない。
関係性とは、意識的にであれ、無意識的にであれ、彼を何者かとして認識したときに決定されるのだ。
だが、われわれは常に順番を逆にして考えがちである。
まず「家族」というこの世界にある価値を大前提にし、そこに一人一人を、「妻」「父」「子」といった形で埋め込んでいく。
理想的な(イデアとしての)関係の配列のもとで考えられた家族を基準として、われわれの関係は誤解されていくのだ。
この映画が示すのは、既存の価値に染まった「家族」というものの無価値さである。
そして、集団性を形成するのは、常に関係が先行するということなのだ。
星座=配置(constellation)としての「家族」
では関係の先行性とはなにか。
それは一人の人間において、あるいは一つの事物において、あらかじめ定まっている関係などひとつも帰属しないということである。
つまり、われわれの中に「家族」という既存の諸価値はインストールなどされていないのだ。
したがってどの人間のまとまりにも「ある一つの集団性」があるだけで、それが無数に点在していることになる。
ゆえに、「万引き家族」も、われわれの「家族」もその意味で「一義的」、つまり同じ意味であるのだ。
決して「万引き家族」だけが特殊で特別な家族なのではない。
根本において、ある集団性があるだけなのだ(一義的)。
しかし、その集団性の内実は多様である。
そこで暮らす人々はどんな構成をしていて、どんな役割をもつのか。どんな言葉で会話し、どんな身振りをするかは、それぞれによって差異があるのだ。
この多様さは関係が先行しているからこそ、顕在化してくるのであり、この関係そのものは常に変化していくこととなる。
それはあたかも星座のごときものであろう。
点々と存在する星と星を線で結ぶことによって、われわれはあるまとまり(集団)を「蟹座」と呼ぶであろう。
しかし、この星々の結びつきは、別の星を加えたとき形を大きく変える。
関係性が先にあり、この関係が変化することで、その集団性がもつ内実も大きく変わっていくのである。
万引き家族とは、われわれが知らない星座である。
あるいは、都会において不可視なものとされた星座の別名なのだ。
彼/彼女ら家族を、単純に「擬似家族」という、真なる「家族」の劣化コピーに堕してはならない。
彼らこそ、新たな集団性を生きているのだから。
あらゆる生を肯定するために
高貴な、あまりにも高貴な人間
彼/彼女らはあまりにも高貴である。
彼/彼女らは自らの生を呪詛しない。
労災がおりなくても、不当にも解雇を告げられても、彼/彼女らは余裕綽綽に、そして淡々と日々を過ごしていく。
りんが誘拐なのかどうかと考えるときも、焦りの色など微塵もない。
刑に問われることよりも、りんが元の家に帰ったときに、虐待されてしまうことを考えるのだ。
そして金などなくても楽しくやれる。そうしたことを教えてくれる。
それは人を愛し、憎しみをもつことなく、共にあり、やりたいことをやる。
優雅で、しなやかで、気品あふれる強さをもつ。
だから、彼/彼女らこそが「貴族」なのだ。
同情という毒
しかし、そんな「家族」の一員である祥太の高貴さは、駄菓子屋の親父によって歪められる。
「妹にはさせるなよ」
りんに万引きをさせた祥太は、その親父から情けをかけられ、万引きを見逃してもらっただけでなく、お菓子までもらってしまう。
駄菓子屋の親父は、祥太に「同情」という毒を盛ったのだ。
「同情とはなにか。それは零に近い生の諸状態に対する寛容である。同情は生への愛であるが、しかし弱くて、病弱で、反動的な生への愛である」(ドゥルーズ、江川隆男訳『ニーチェと哲学』河出書房文庫、p.293)
たしかに駄菓子屋の親父は自身の優しさゆえに、彼を見逃したのだろう。
しかし、その優しさは、祥太にとって毒であり、祥太自身の生を疾しいものとして否定させる。
だから祥太はわざと万引きをし見つかることを選んだのだ。
祥太に芽生えたのは、「恥辱」である。
高貴であることに対する恥。
それに追い討ちをかけるように、マスコミや警察は、彼らに疾しさを植え付ける。
状況にまったく一致しない報道をし、騒ぎ立て、治と信代の過去をほじくり返し、それによって彼らを既存のなにがしかに当てはめようとする。
法は一つの暴力として、単に書かれた内容を反復し、りんを虐待する母親のもとに送り届ける。
たった一つの同情が、一人の高貴な生に苦しみを与えたのだ。
辱めることをやめよ
治も信代も当たり前のように、祥太に対して恥辱を与えることはしない。
ニーチェはいう。「高貴な者は、ひとを辱めまいと自らを戒めている、またすべての苦悩する者を前にすれば恥辱を感じよと、自らを戒めている」(ニーチェ『ツァラトゥストラかく語りき』佐々木中訳、河出書房文庫、p.147)
彼/彼女らは戒めているのだ。
だからこそ信代は祥太を拾った場所を伝え、治は自ら父親であることを放棄する。
祥太に同情してしまうとき、彼らは遠くからするのであり、顔を隠してその場から去るのである。
また祥太自身も自らの高貴さを取り戻す。
父から叔父になると伝えられても、彼はただうなづくのみである。
バスに乗り込む時も淡々とし、優雅に振る舞ってみせる。
それはそれぞれが自らの生を肯定するからであり、それぞれが同情することで恥辱を与えてしまう自分に対して、恥辱を感じているからにほかならない。
それでも、別れとは高貴なものにも動揺を与える。
治はバスを追いかけ、祥太は小さな声で「父ちゃん」と呟く。
われわれが最後、涙するのは決して同情のためではない。
彼らのあまりにも高貴な姿を目にするがゆえに、泣いてしまうのだ。
最後に
いい映画、いい音楽とは常に、われわれの中にある種の違和感を刻み込んでくるものである。
いい作品とは、観るものの本質を変形すると同時に、作品自体の本質も変形していくものである。
こうしたことのない作品は、どんなに耳障りのいいものでも、駄作である。
さて、われわれに高貴な人間は見えているのだろうか。
われわれは、自分にとって都合のいいものしか見ていないのだから。
そして、見えたとしても、そんな彼/彼女に同情してはいないか。
われわれの同情は常にその人の生を疾しいものに変えてしまう。
必要なことは彼/彼女の生を絶対的に肯定することであり、自らの生を絶対的に肯定することである。
われわれは「万引き家族」を、同情の感情をもって観てはいけない。